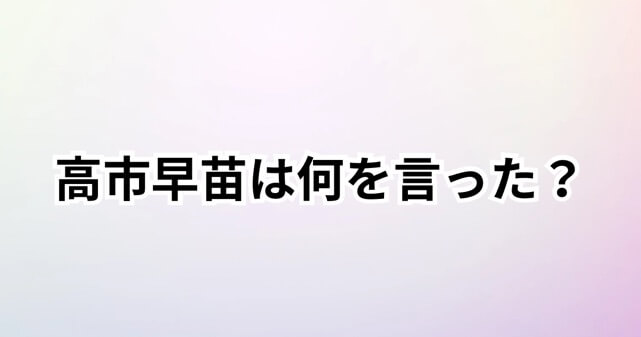高市早苗首相の“台湾有事”に関する発言が大きな注目を集めています。
「何を言ったの?」「なぜこのタイミングでそんな発言になったの?」と疑問に思う人が多いはず。
そこで本記事では、① 高市氏が実際に何を言ったのか、そして ② なぜその発言に至ったのか(経緯) に絞って、分かりやすくまとめました。
高市早苗首相は「何を言った」のか

2025年11月7日の衆議院予算委員会。
台湾海峡で武力衝突が起きた場合の日本の対応について問われた高市首相は、次のように答弁しました。
「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」
これは、
- 日本が直接攻撃されていなくても
- 台湾で武力衝突が起きれば
- 日本の安全が重大な危機にさらされる可能性がある
という見方を示したものです。
「存立危機事態」とは、日本の存立が脅かされる明白な危険がある状態を指し、
この認定がされると 集団的自衛権の行使が可能になる という非常に重要な概念です。
誤解されがちですが、この答弁は「日本が台湾有事に即軍事介入する」と表明したものではありません。
高市首相が述べたのは、法律上“存立危機事態に該当する場合があり得る”という可能性の説明であり、具体的な武力行使や介入の決定を示すものではありません。
また高市首相は発言後、
- 「従来の政府見解を踏まえたもの」
- 「言葉の使い方は今後さらに丁寧にする」
と補足し、意図はあくまで法制度上の説明であると強調しました。
なぜこの発言に至ったのか(経緯と背景)
●背景:台湾情勢が緊張していた
近年、台湾海峡では緊張が高まり続けていました。
日本周辺でも台湾関連の安全保障議論が増えており、国会でも「台湾有事の際の日本の対応」は頻繁に問われるテーマになっていました。
そのため、質問自体が増え、避けて通れない状況にありました。
●直接のきっかけ:国会質疑で具体的に問われた
予算委員会では、野党議員から
「台湾とフィリピンの間で紛争が起きたら、日本はどう判断するのか?」
という、具体的なシナリオを伴う質問がありました。
これに答える形で、高市首相は
「状況次第で存立危機事態に該当し得る」
と説明したのです。
= 誘導型の質問に対して、法的枠組みをそのまま答えた結果として出た発言
という構造になっています。
なぜ高市発言はここまで波紋を広げたのか
高市氏の今回の答弁が大きく取り上げられた背景には、日本がこれまで台湾問題で取ってきた“あいまいさ”から一歩踏み込んだ印象を与えたためという指摘があります。
● 日本は長年「戦略的あいまいさ」に近い立場を維持してきた
台湾をめぐっては、アメリカが長年
「戦略的あいまいさ」(中国が侵攻した際の対応を明言しない方針)
を採用しています。
この「あいまいさ」は、中国に対して
- 軍事侵攻はコストが大きい
- しかしアメリカが必ずしも介入するとは限らない
という“複数の可能性”を考えさせることで、抑止力として機能してきました。
日本もこの考え方に近く、
「台湾問題は対話での平和的解決を望む」
という公式立場に留め、政府関係者は安全保障の場で台湾について触れることを避けてきました。
● 高市氏の発言は「踏み込んだ」印象を与えた
しかし今回、高市首相は国会で
「台湾有事が日本の存立危機事態に該当し得る」
と答弁し、日本の安全保障と台湾情勢のつながりを明確に示した形になりました。
これは、従来の“あいまいさ”や配慮のある表現から踏み込んだ発言だと受け取られ、
国内外で大きな反響を呼んだと見られています。
● 中国が強く反発した背景にもつながる
日本が台湾問題に関して踏み込んだ姿勢を示すことは、中国にとって敏感なテーマです。
そのため今回の発言は、中国側が「日本が台湾問題に関与する姿勢を強めた」と受け止め、強く反発した背景にもなっています。
まとめ
- 高市首相は国会で
「台湾有事が起きれば、日本が存立危機事態に該当し得る」
と発言した。 - この発言は、
台湾情勢の緊迫化・国会質疑の流れ・安全保障に強いスタンスを持つ高市氏の姿勢
が重なって出てきたもの。 - 特に
「具体的な有事シナリオを問われた → 法的枠組みを説明する必要があった」
というのが、発言の最大の経緯と言える。